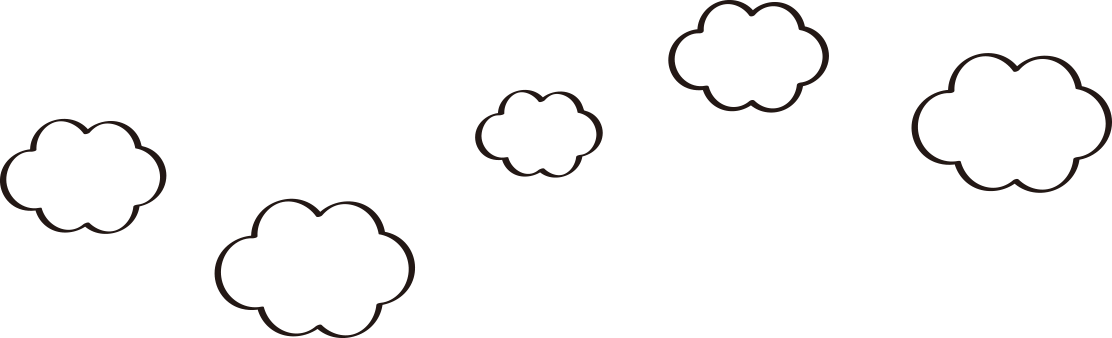
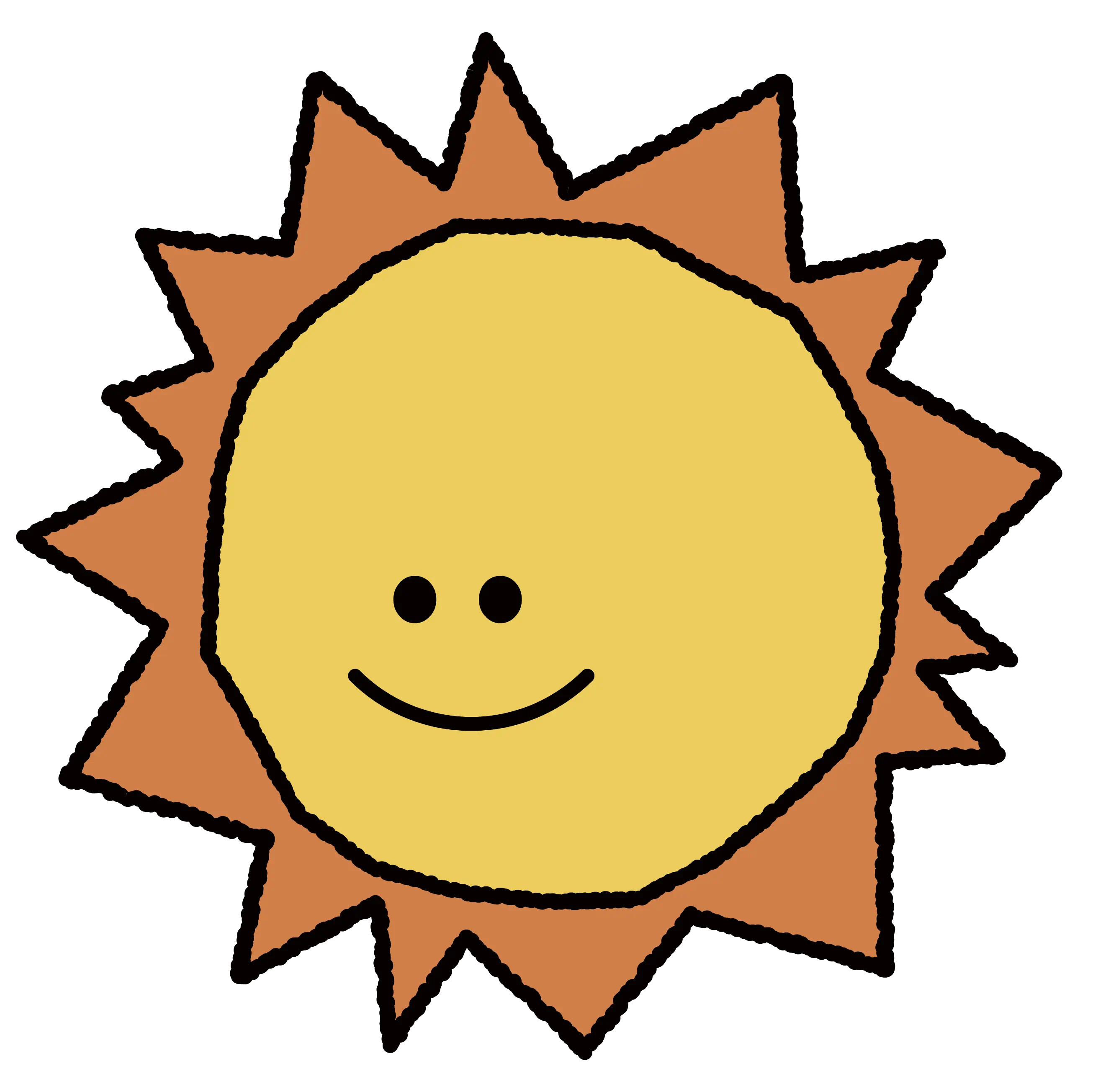
保育の考え方
明るく元気な子ども・自主性のある子ども・仲間を大切にする子ども
良く観て、よく聴いて、よく考えるこども・自分のことは自分でしようとする子ども、
人と関わる力のある子ども




保育の考え方
0歳児の目標
- 担当制を通じて、しっかりした人間関係をつくる。
- 一人一人のこどもの気持ちを受容し共感しながら継続的な関係を築く
- オムツ交換や衣類の着脱などを通じて清潔になることの心地よさを感じる。
■保育士の配慮
- 温かく、受容的な関わりを通じて自分を肯定する気持ちの芽生えを促す。
- 育児の担当制を行い、子どもの発育・発達の変化を細かく把握し、順序性をおさえて必要に応じた援助をする。
- 基本的信頼の確立をはかるため、大人との一対一の関係を大切にし、共感、見つめ合う、うなずき合う等心地よく過ごせる環境を整える。
■ 離乳食の進め方の目安
| 離乳の開始 | → | 離乳の完了 | |
|---|---|---|---|
| 生後5,6ヶ月頃 | 7,8ヶ月頃 | 9ヶ月から11ヶ月頃 | 12ヶ月から18ヶ月 |
|
|
|
|
※横にスクロールします
1歳児の目標
- 一人一人のこどもが安定感をもって過ごせるようにする。
- 保育士の応答的な関わりや話しかけにより自ら言葉を使おうとする。
- 基本的生活習慣の習得に向かう環境をつくる。
- 走る、跳ぶ、登る。押す、引っ張る等の全身を使う遊びを楽しむ。
■保育士の配慮
- 「○○したい」「自分で」など思いやつもりが育つ時期、自我の芽生えを受けとめ、生活の流れを丁寧に組み立てて見通しのもてる安定した生活をつくる。
- ぶつかり合ってそれぞれの思いが大事にされ、納得し、友だちと楽しく共感できる力をつける基礎をつくる。
- 自分の思いやつもりでじっくりあそび込み、納得できるよう配慮する。
- 2歳の誕生日までに、オムツをはずせるよう取りくむ。
- 排尿が完成した時、人として初めての自立(もう赤ちゃんではない)
- 完ぺきな歩行に向かう → 一気におしゃべりという課題へ。
2歳児の目標
- 一人一人の子どもが周囲から主体として受けとめられ主体として育ち自分を肯定する気持ちが育まれるようにする。
- 自分のものと、人のものの区別や場所的感覚等環境を捉える感覚が育つ
- 基本的生活習慣が心地よい感覚として身につくようにする。便器での排尿になれ自分で排泄ができるようになる。
- 生活や遊びの中で経験したことを自分なりに表現する。
■保育士の配慮
- しっかりした自我の確立に向け、子どもの気持ちをくみとり、気持ちを切り替え、少し先の見通しがもてるよう支援する。
- 1人ひとりの子どもが安心して言いたいことや、やりたいことが表現できるよう配慮する。
- 意欲的に取りくめる生活とあそびを目指して、乳児期から幼児への転換期を丁寧に受けとめる。
- 0歳
- 基本的信頼が確立され
- 1歳
- 自分をしっかり受け止められて、基本的生活習慣の自立に向けて保育されてきた食事・排泄・睡眠・着脱・清潔
- 2歳
- 自分で食べて、眠ったり、トイレに行け、服を脱いだり着たり、また、あそんだおもちゃを促されて片付けられる→できるようになったけど、大人に支えて欲しい気持ちもある。見てるから、自分でやってごらん。

3才~就学までを見通した保育
基本理念
-
子どもの自主性(やる気)を引き出す。
子どもが自分を取り巻く社会を理解する為には、自主的取り組みと維持が重要であり、自主性を育むためには、「認められたい」「自信を持ちたい」という養護的欲求を満たす支援をする。
-
保育者の自主的働きかけ
子ども達に自主性を育むためには、保育者が子どもの要求を考慮し、安心できる保育環境の提供、情緒的な支援、安らぎを与える働きかけなど支援方法に段階を持ち、教育的支援が必要。
-
寄りそうこと
アタッチメント(愛着)理論は子どもと保育者との関係にも当てはまります。
子どもが安心して探求活動をするために、保育者と子どもの良好な信頼関係が必要です。
-
距離をおくこと
目の前にあることだけを学ぶのではなく、目に見えないものにも焦点をあわせる学びです。具体的なことから取り組み始め、徐々に外の世界や抽象的な世界へと興味、経験の幅を広げていきます。
■ 保育士の関わり方
- 子どもへの愛情と信頼関係の構築が土台。
- 温かく見守り、時に子どもと共に考える。
- 集団ではなく、子ども一人と向き合う。
- 与える、教えるのではなく、子どものあそぶ(学ぶ)意欲を引き出すことが大切。
- 基本的生活習慣
食事・排泄・睡眠・清潔・着脱 → 健康の保持と増進をはかるための活動。
食事や午睡の準備、片付け、部屋の掃除、物の管理、整理整頓 → みんなで一緒に生きる力
3歳児の目標
- 一人一人の子どもが自分の気持ちを安心して表すことが出来る。
- 自分の身の回りのことなどを自分でしょうとする。
- 保育所生活を楽しみ自分の力で行動することの充実感を味わう。
- したり、見たり、聞いたり、感じたり、考えたりしたことを、自分なりの言葉で表現する。
■保育士の配慮
- 全身運動の基礎が一定身につく。身体の主人公
- 楽しい遊びを経験しながら学びにつなげていく
- 初歩的なクラスの共感関係を築く
- 子どもたちがあそびたくなる環境がある(ワクワク感)
4歳児の目標
- 一人一人のこどもがくつろいで共に過ごし疲れが癒されるようにする。
- いろいろな遊びを通じて物事をやりとげようとする。
- 想像の世界を豊かにしていく環境をつくる
- 自分の気持ちや行動がコントロールでき、言葉で相手に伝えられるようにする。
■保育士の配慮
- がんばったことをみんなの中で評価する。がんばったことが見えやすくわかりやすい取り組みをする。
- 面白かった、またしようと思える経験。明日も保育園に行きたいなと思える生活。失敗を許せるなかま。
- 自分のことは自分でする。1人ひとりが生活の主人公。~だけれども~する。遊びたいけど着がえてする。
- クラスみんなで約束やルールを守る取り組み。ルールが明確である。
- “○○ちゃんも○○ちゃんもできる。ボクにはできるかな”“できそうもない、やめておこう”他と比べ、自分がみんなの中でどんな位置にあるのか、内面的な世界を成立させて行く。内面の葛藤 → 前向きになれる励み。
※ 友だちといることが居心地よく、気持ちがよい。どんな自分であってもいい生き生きとす
ごせる。お互いを認めあえるクラスづくり
今は何をするとき「ここは何をする所」が明確である。
5歳児の目標
- 一人一人のこどもの健康増進が積極的に図られるようにする。
- 社会生活における望ましい習慣や態度を身につける。
- 友だちと協力する活動を十分保障する。
- 自分の役割がわかる
- 話し合いで解決できる
- 感情の抑制ができる
- ルールのあるあそびができる
■保育士の配慮
- 就学に向けた社会性を身につける取り組みをする。
- 生活や遊びを通して、決まりがあることの大切さに気付き、自らが判断して行動できるよう配慮する。
- ルールが明確である。言葉で行動をコントロールできる。目標に向かって粘り強く挑戦できる。
- 秩序だった生活の中で社会性のスキルが身につくよう配慮する。



卒園までに育てる10の姿
-
自立心
しなければならないことを自覚し、それを行い認められることで達成感を味わい自立心を養う。
-
言葉
自分の経験したことや考えたことを言葉にして相手に伝え、相手の話を聞こうとする。
-
協同性
自分の考えや気持ちを伝え、友達とイメージを共有して試行錯誤しながら工夫して遊びをすすめる。
-
健康
自分なりの目標をもって色んな遊びに挑戦し、達成するために工夫し繰り返し取り組むことで健康の増進を図る。
-
道徳、規範
グループの中で話し合って役割を決め、遊びのルールを作りみんなで遊びを発展させることで道徳心や規範の意識を高める。
-
社会生活
住んでいる地域社会とのつながりを意識するようになり、地域の行事に参加し、小学校に見学に行くことで就学を意識し、地域の中に住んでいることに気づく。
-
思考力
見通しを立てて制作や遊びを工夫する。「こうすればこうなる。」という見通しをもって制作し、友達と意見を出し合って遊びを工夫することで思考力をつける。
-
自然・生命
命の大切さや自然の不思議に気づく 自分たちで虫や小動物を飼育し、植物の世話をする中で、動植物に愛着を持って関わり、命の大切さや自然の不思議さに気づきいたわる気持ちや恐怖の念をもつ。
-
数量・図形・文字
遊びの中で文字や数量を使い、興味、関心を深める。
友達にお手紙を書いたり、買い物ごっこや、トランプ等のカードゲームをして文字や数量を使った遊びを楽しみ文字や数量に触れることで使おうとする。
-
感性 表現
自分が表現したいことを、言葉や身振りを通して伝え、友達の意見を取り入れながら、劇や歌、作品作り等の表現活動に取り組むことで感性を育て表現力を身につける。
■ 生活の管理は大人の責任で
- 生活時間を規則正しくする
- 食事はどのように食べるのか
- 持ちものは、どこにどのようにおくのか
自分の生活がどのような仕組みになっているのか、大人が見せていくことが必要。
仕組みがわからなければ、判断することができないので。
■ そして保育園は、子どもにとって第2の家
- おじいちゃんやおばあちゃんの家に行くような自分の家庭に一番近い雰囲気の中で生活できる。
- 決まった場所、決まった時間、決まった仲間など、子どもを取りまく環境の中で繰り返される事柄、秩序をわかりやすく見せて行く保育
- 子どもの育つ力を信頼することから保育は始まることを確信して、保育にあたる。
